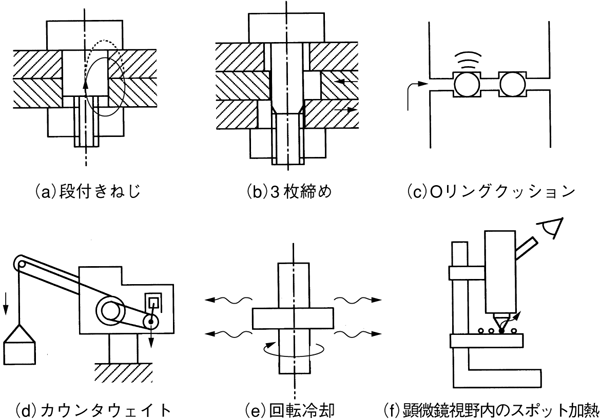
図 各種の“一人二役”機構
たとえば、ボルトとナットによる板の締め付けを考えよう。ボルト・ナットは2枚の板を締結させるだけに使うべきで、図(a)に示すように、ボルトを段付きにしてピン代わりに位置決め用としても使うと、問題が生じる。少しでも2枚の板の穴の中心が合わないとピン部の摩擦力が大きくなり、ねじを締めても、図に示すように力線がボルトの頭の部分を通らず、ピン部の側面を通るようになる。トルク管理して締め込んでも、何かの拍子で穴がずれて摩擦力が小さくなると、ねじがゆるむことになる。また、図(b)のように1本のボルトで3枚の板を固定すると、締めて組み立てた後で、真ん中の板をずらそうとゆるめた時、上下の板もずれてしまう。また、Oリングをシールだけでなく、クッション代わりに使うこともあるが(図(c))、中途半端なつぶし代を採用することになるから、シールが不十分になる。この他に、エンジンを動力源だけでなくカウンタウエイト代わりにも使ったり(図(d))、回転軸を伝動のためだけでなく空気流を誘起して装置の冷却のために用いたり(図(e))、光学顕微鏡を観察だけでなくスポット加熱のために用いたり(図(f))、というように一人二役の悪例は多々ある。(参考文献:中尾政之、畑村洋太郎、服部和隆「設計のナレッジマネジメント」日刊工業新聞社)
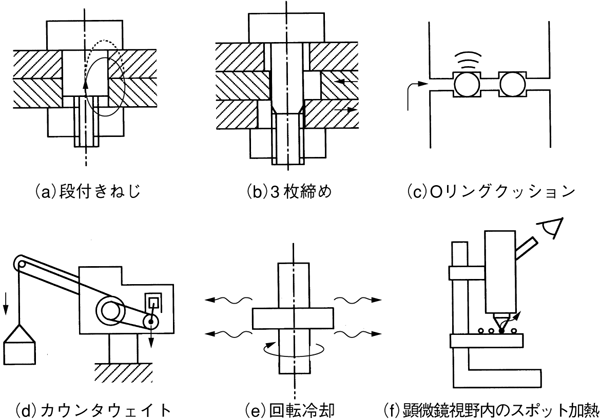
【思考演算の説明】
一つの機構に二つの機能を行わさせると、一挙両得で“賢い”設計であると誉められる。その一人二役をする機構によって最適化された製品自体はすばらしい。しかし、一般に言えることであるが、それをちょっとでも改造設計した途端に問題が噴出してくる。なぜならば、このように機能と機構との関係に干渉成分が存在すると、一つの機能を調整しようと欲して、それに対応する機構を変えると、変えたくないはずのもう一つの機能まで変わり、“にっちもさっちもいかなくなる”からである。